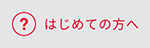New Balanceの価値観である
“オーセンティシティ(=“真実性”、“本物であること”の意)”は、
常にアスリートによって表現されます。
では、アスリートとは何か?
NB20000は、この途方もない問いに対する解答です。
【12/23(月)9:59まで】myNB会員限定 全品送料無料!
年内のお届けは12/26(木)15:00ご注文分まで! 詳細はこちら

NB20000とは、
アスリートの本質的な魅力に触れ、保存価値のあるアーカイブを作るNew Balanceのプロジェクトです。
アスリートと向きあい、つむぎ出された言葉の数々は、文字にして20,000字超におよびます。
ときに時制を巻き戻し、瞬間瞬間の心象を紐解き、内面にせまる。
定型化した一問一答の勝利インタビューでは表現しきれない言葉を集め、群を抜いたボリュームで強さの根源を探ります。
田中希実
1999年9月4日生まれ。兵庫県出身。豊田自動織機所属。2014年に中学生で全国都道府県対抗女子駅伝競走大会に兵庫県代表として出場し、8区区間賞を獲得。翌年も8区を走り区間賞を獲得。西脇工業高校に進み、第70回国民体育大会では1500mで優勝、翌年71回大会では3000mで2位、72回大会では3000mで優勝。2016、2017年は全国高校駅伝に出場。2018年都道府県対抗女子駅伝では1区を走り兵庫県の優勝に貢献。アジアジュニア選手権では3000m大会記録で金メダルを獲得。世界ジュニア選手権でも3000mで金メダルを獲得。ジュニア世代を牽引する存在として活躍を続けてきた。2020年日本選手権5000m優勝、2021年日本選手権1500m優勝。東京2020オリンピック女子1500mに出場し、日本人初決勝進出し8位入賞。2022年世界陸上では800m、1500m、5000mの3種目に出場。同年9月にニューヨークで開催されたマイルロードレース 5thアベニューマイルに初出場し、女性の部5位。日本陸上界を代表する存在のひとりとして、世界へチャレンジを続ける。
もっと先へゆくために。
新たな挑戦を楽しみながら、流れに身を委ねたい
田中希実らしさとは、何だろう。彼女の静かな瞳が映しているものは、ただ競技成績やレースの経緯を振り返っていても、きっと見えてこない。鍛錬とか勝負とか、挫折とか孤独とか高揚とか、そういうものを積み重ねて、彼女の内側からにじみ出てくる言葉があるはずだ。
ランナーの両親を持ち、物心ついたときには走ることが身近にあった。幼いころから読書に親しみ、本の世界に没入する感覚が好きだった。走りはじめてからも、その研ぎ澄まされた心と体の感覚を、楽しんでいる。自分を大きくも小さくも見積もらず、まっすぐに前を見て、やるべきことを手繰り寄せていく。
彼女は何を思って走ってきたのか、そして、何を思って走っていくのか。これは1999年9月4日から、2022年5月11日までの田中希実に迫った記録である。

01 : 流れ
この流れになんとか逆らえないかと、
もがいた
22歳の田中希実が、入社式で掲げた目標は「流れにまかせる」だった。何も考えずにいると、つい流れに逆らおうとしてしまう。そのもがきが、レースでの快進撃につながることもある。だけどこれからはきっと、いままでどおりじゃ闘えない。だから、これまでの自分をふまえたうえで、あえて逆の「流れにまかせる」を決めたのだ。

静かなまなざしが印象的だ。みずからの内面に深く潜っているようにも、ただ前だけを見つめているようにも思える。もしかしたら田中希実は、もうずいぶんと遠くまでを、自身の射程距離に収めているのかもしれない。
世界の名だたる大会で堂々たる走りを見せてきた彼女は、じつはまだ22歳だ。
この春に同志社大学を卒業し、社会人になった。株式会社豊田自動織機への入社にあたって、記者会見では「流れにまかせる」という抱負を発表している。ヘルマン・ヘッセの本『シッダールタ』や、夏目漱石『草枕』からインスピレーションを得た言葉だ。

「大学を卒業してから、練習場所や大会、遠征先にいる時間がぐっと増えました。陸上一本になったから、去年までよりは競技に集中できる環境にもあるはず。だけど、大会への出場が多いからか、気づいたら時間が経ってしまっているように感じています。いまの調子がいいのか悪いのかも、あまり実感がありません。でも、しばらくはこうやって、流れに任せていていいのかもしれないと思っています。性格的には流されるのがいやなタイプだし、ほうっておくと流れに逆らおうとする傾向があるから、あえてそんな抱負を掲げました。言葉どおりの日々を送れているかは、謎ですが……」
落ち着いて言葉を選びつつも、おだやかな表情で答える。
そして、流れに逆らっていた近年の例として、2020年から翌夏までのシーズンを挙げた。新型コロナウイルスの感染拡大で思うように練習できないことも増えるなか、田中希実が、着実に名を上げていった時期ともいえる。
まず、その前年の2019年世界陸上競技選手権大会(カタール・ドーハ)にて、5000mで当時の日本歴代2位タイムをマーク。2020年7月のホクレンディスタンス深川大会にて、3000mの日本新記録(8分41秒35)。続いて2020年8月、セイコー・ゴールデングランプリ1500mで14年ぶりに塗り替える日本新記録(4分05秒27)。さらに、2021年7月ホクレンディスタンス網走大会3000mでは、前年に打ち立てた自身の日本記録を更新(8分40秒84)。と、次々に国内記録を塗り替えていった日々だ。


「あのときは、流れに逆らうに近かったと思っています。自分のいまのポジションもわからないし、コロナ禍でいろんな大会が中止になって、力を発揮できる場所もない。そうすると、目の前のきつい練習に耐える意味が見いだせなくなっていくんです。いつかはかならず大会が再開されるとは思っていても、それがいつになるかはわからないから、自分を律し続けることが難しくて……とにかくきつかったですね。この流れになんとか逆らえないかと、もがいていました」
緊急事態宣言下の練習を支えたのは、非日常に生まれたコミュニティだったという。
「日ごろは関東に出ている学生が戻ってきたり、部活ができなくなった地元の高校生が集まったりして、感染対策を講じながら一緒に練習するようになったんです。自粛などのフラストレーションはあったけれど、反面、バラバラになっていた仲間とまた走れるのはうれしかったですね。高校時代は部活で誰かを追いかけたり、誰かに抜かれないようにしたり、集団のなかの自分の位置をつねに意識しながら練習していたんです。でも、大学に入ってそういう視点からは少し遠ざかっていたから、ひさしぶりにその感覚も味わえました。現役女子高生と走るときは先輩として引っ張ったり、逆に男子選手には何も考えずくらいつく面白さがあったり。走る前にはピリピリして、走ったあとにはみんなでふーっとくつろいで……部活の日々がよみがえったみたいでした。苦しい時期だったけれど、非日常のいい経験だったなって思います」

そんなコロナ禍初期のもがきが、以降はいい反動を生んだのだろう。2020年のホクレンディスタンス深川大会が開催されると決まってからは、練習にも弾みがついた。
「7月にホクレンで走るための練習だって明確に目標が見えたおかげで、ぐっと気持ちが上がっていきました。これまで積み重ねてきた成果を披露するのが、楽しみで仕方なくなった。この大会は、当時まだポピュラーではなかったオンライン配信が決まっていました。世の中の雰囲気がどうしても暗いなか、陸上競技を取り巻く状況を気にしてくださっている方々もたくさんいたし、ここで日本記録に届くような走りをしたらきっと喜んでもらえる、と思っていたんです」
前半で逆らってきた流れは、そのまま急流となり、そこからの快進撃をあおっていく。果たして彼女はその大会で、福士加代子の日本記録を18年ぶりに更新し、ゴール。狙いどおりの結果を出した。


02 : 没入
本の世界に入り込んでいるときも、
本当に集中して走れているときも、周りの声は聞こえなくなる
両親の影響を受けて、幼いころから彼女は走っていた。一方で、心静かに読書をするのも好き。本の世界に没入する感覚と、いま走りに集中しているときの感覚は、少し似ているかもしれない。なんとなくはじめたランが未来とつながってきたのは、高校に進んでから。徐々にレースで結果が出せるようになり、世界への扉が開きはじめた。練習や学業に忙しい日々でも、彼女はどこか超然としている。「自分の限界を見てみるか」なんて、こともなげに言いながら。

田中は、陸上一家の生まれだ。いまではコーチを務める父・健智は、元3000m障害の選手。母の千洋も、北海道マラソンで2度の優勝経験をもつ市民ランナーである。日本で初めて、産後に2時間30分を切る記録を出した。
さまざまな市民マラソンで活躍し、海外大会にも招待される母の姿を見て、少女だった田中は「自分もいろんな国に行ってみたい」と思うようになる。3歳から少しずつ走りはじめ、初めて海外大会を経験したのは11歳のとき。母が派遣されたゴールドコーストマラソンに同行し、キッズの部で優勝を飾った。

でも、当時走ることよりも強く彼女の心を奪っていたのは、本の世界だったという。メディアでもたびたび登場する田中の読書好きは、筋金入り。きっかけは、小学校3年生の国語の授業だった。
「みんなの前でお気に入りの本を紹介することがあって、好きだった『赤毛のアン』や『大草原の小さな家』『アルプスの少女ハイジ』なんかを勧めたんです。たくさんの本を知っていることを周りに褒められて、うれしくなり、いっそう読書にハマっていきました」
学校が終われば、少しでも早く本を読むために、家まで走って帰る。小学校から家までは約2.5km。小学生の足では、歩けば30分以上かかる距離だ。その時間が結果的によいトレーニングとなり、脚力の下地をつくったことは想像に難くない。
「読書をしていると、頭をからっぽにして本の世界に入れるのが面白いんです。昔はそこまで速くも走れなかったし、走ること以上に読書が自分のアイデンティティでした。陸上を競技として見ていなかったこともあって、選手より作家になりたいと思っていたくらい。ただただ、本を読むために走っていたんですよね。いまはなかなかそこまで読書にのめり込む時間がとれないけれど、本の世界にうまく没入できたときは、小学生のときと同じようにすごく楽しいです」

全力で身体を動かすとき、頭が真っ白になると表現する人は多い。日々の雑事を忘れ、目の前のことに取り組める感覚が気持ちいいからと、日常的にスポーツの時間をとる人もいる。田中にとって、頭をからっぽにして本の世界に身を投じる感覚と、走りに集中する感覚は、どこかでつながっているのだろうか。
尋ねてみると、彼女は「走ることと読書をつなげようとはしていませんが……」と前置きをして、言葉を続ける。
「走ることは肉体的なきつさも伴うから、やっぱりまったく同じではないですよね。でも、没入感という意味では似ているかもしれません。本の世界に入り込んでいるときも、本当に集中して走れているときも、周りの声は聞こえなくなる。というか、気にならなくなるんです。その、なんだかよくわかんないけど脚が動く感覚が、すごく楽しいと思えたりする境地もあります。そういう軽いランナーズ・ハイのときと、どんどんページをめくりたくなるような高揚は、近しいものがある気がしますね」

ただ本を読むために走っていた時期を過ぎ、少しずつ、彼女のアイデンティティは変化していった。中学の陸上部で本格的なトレーニングをはじめ、いつのまにか読書よりも陸上のほうが、彼女のなかで大きな存在感を放つようになる。「大人になったら、自分もマラソンをやるのかもしれない」――そのくらいにあいまいだった未来の輪郭がはっきりしてきたのは、高校に進んでからだ。
地元の兵庫県立西脇工業高校では、多くの全国大会に出場。当時は駅伝にも力を入れていたため、1500mや3000mといった個人種目にばかり集中できていたわけではない。それでも、高校2年の日本選手権では1500mで2位に入り、翌年の国際大会にも派遣された。
「一応インターハイで活躍できるレベルにまではなれていたけれど、このままシニアにいっても全然通用しないだろう、と感じていました。日本選手権で2位になれたときは希望が見えたものの、コンディションがちょっと悪いとすぐ6位になったりして、全然安定しない。絶対にいつでもメダルを獲れるとまでは思えないし、絶対にいつでもメダルを獲れるようにならなくちゃ、国際大会では活躍できないんですよね。走りで世界を見てみたかったけれど、見られるレベルにはまだまだ届いていない気がしていたんです。振り返れば、中学の陸上部で走っていたときのほうが、もっと上にいきたいという野心も強かったように思います。高校時代はどちらかというと現実が見えてきて、そのときそのときを過ごすのに必死でした」
つまり彼女の高校時代は、いい選手や機会に恵まれて、多くの刺激を受けた3年間だったともいえる。ひたむきに努力しなくてはいけないと思えるだけの、原動力を持てていたのだから。1年生で、国内のトップ選手を集めた研修に参加したときの出来事も、強く印象に残っていた。
「コーチから『世界で活躍できるようになるための覚悟があるか?』といったことを聞かれたんです。でもそのときは、すぐ上にいる2年生や3年生の先輩にさえ全然勝てなかったんですよね。そんな状態で、世界なんてまったくイメージできない。それどころかシニアは年齢に区切りがないから、強い選手が増えていく一方です。どれだけのし上がっていけばいいのか、まったく想像がつきませんでした。でも、自分が世界的な大会に出られるような選手になるためにはどうすればいいか、はじめて冷静に考えることができた機会でもありました」

そこからまた、目の前の壁をひとつずつ乗り越えていくべく、がむしゃらに走り続けたのだろう。もしかすると、彼女の性格からして、それしかできなかったのかもしれない。結果、大学1年のときにはアジアジュニア選手権の3000mで、金メダルとともに大会記録を更新。U20世界選手権でも、3000mで金メダルを獲得した。世界への扉が、徐々にひらいてきた。
もちろん、大学の勉強と陸上競技の両立は簡単なことではない。スポーツ健康科学部に在籍しながら、授業の合間に練習を重ねた。
「高校を卒業して陸上一本でやっていく選手も多いけれど、私は陸上以外の世界も知りたくて、また、学問の知見からも陸上を見たくて大学に進みました。だから、大学時代は授業がメインで、すきまを見つけては練習を詰めていく日々。でも、母が市民ランナー上がりだから、仕事の合間に練習を入れる生活が当たり前だったし、理解も示してくれました。授業や大会で忙しい時期は、体力的にも精神的にもきついことはあったけど……両立を目指すスタイルでやっていてよかったと思います。むしろ『こんなにぼろぼろの状態でレースに出たらどうなるんだろう? ちょっと自分の限界を見に行ってみるか』って、逆に面白くなってきちゃったりして」と、笑う。
ほかの選手は誰もこんなスケジュールで練習をしていないはずだ。そう思うと、あえて苦しい道を選んでいる自分を誇りに感じることもあった。
「卒論提出前は大変でしたね。データ集めだけはしていたけれど、分析したり論文を読んだりはまったくしていなくて、締切1ヶ月前から着手。それからはもうてんてこまいでした。でも、そういう時期を経て卒業したいまは、思いきり陸上に打ち込めるようになった解放感があります。ずっとこの状況が続くわけだから、途中でまた学生時代みたいにメリハリをつけたいと思ったりするかもしれないけど……。しばらくは、しっかりと陸上中心で。ゆくゆくは、これまで学校が占めていた時間を使って、なにかメンタルを整えるようなことができたらいいなと思っています」

田中が昔から、読書と同じように続けてきたことがもうひとつある。日記だ。
アンネ・フランクの伝記を読んだことをきっかけに、毎日少しずつ出来事や気持ちを記すようになった。一日の終わりのたった20分ほどだけれど、自分をまなざす時間。忙しくても簡単なメモをとり、13年間書き続けている。
「日記にいまの自分の感情をそのまま書き込めたら、気分がすっと落ち着きます。そういう日には、書いているだけで時間も忘れられる。日記を書くことが、気分転換や気持ちの整理になっているんですよね。でも、日によっては書く気になれなかったり、自分の気持ちなんて見つめたくないと思う日もあって……うまく言葉がつながらず、出来事をバラバラに羅列するだけになってしまったりします。書くことをどう感じるか自体が、心のバロメーターになっているのかもしれません」
いつのまにか、日記を書くことは陸上競技を続けていくうえでも欠かせないツールとなっていたようだ。自分の状況を書き出して俯瞰することが、大きく役立つのだろう。この数年は自分の筆だけに頼らず、周りの声を聴いてみることも覚えた。信頼できる人にいまの気持ちを吐露したり、大会の感想をもらったりすることも、心の整理に役立つ。自分をわかってくれている人の客観的な言葉で、落ちていた気持ちが立て直せることも少なくない。


03 : 心地よさ
自分が、大会の一部にちゃんとなじんでいるって、
自信があった
田中希実が、いよいよ世界に駆け出した。思った以上に高い壁を痛感したレースがあれば、いい流れのなかで自分らしいタイムを出せたレースもある。なにより彼女は、自分が世界と闘う場の一部であることを楽しんでいたし、期間中ずっと、不思議な心地よさに包まれていたのだという。そんな大舞台を経た彼女に、陸上そのものを愛したいという思いが生まれたのは、なぜか?

ドーハから一年、ふたたび世界と闘う切符を手にしたのは、大学3年のときだ。2020年12月の日本選手権(第104回日本陸上競技選手権)で廣中璃梨佳と5000mのデッドヒートを繰り広げ、優勝。すでに基準となる記録は突破していたため、廣中に勝った瞬間、田中の出場が決まった。そのまま5000mだけに集中するという選択肢もあるなかで、翌春は1500mのレースを連戦。日本人女子初の1500m代表としても、出場枠をもぎとっている。

「初戦の5000mを走ったときは、自分が大会の大きさに見合っていない気がして、少し収まりの悪さを感じていました。世界と闘うことが、とても大きく見えていたんだと思う」と、当時を振り返る。結果は予選敗退。14分59秒93で走りきり、15分を切っていたにもかかわらず、越えられない壁を痛感した。
「それから数日間を過ごすうちに、少しずつ場の空気に慣れてきた感覚がありました。大きな舞台だからこそ、細かいことを気にせず、割り切っていこうと感じはじめた。続く1500mで結果が出せたのは、そういう気持ちの違いも大きかったと思います」
1500m予選では、自身のもつ日本記録を更新し、4分2秒33で準決勝に進出。2日後の準決勝ではさらに3分59秒19までタイムを縮め、決勝進出を決めた。実戦に入り、大舞台で研ぎ澄まされながらどんどん速くなっていく。彼女は完全に、いい“流れ”のなかにいた。決勝でもふたたび3分台をマークし、メダルには届かなかったものの、日本人初の8位入賞を果たしている。
快走はもちろんのこと、田中が1500m決勝時に見せた表情も話題となった。入場ゲートでは、弾けるような笑顔で飛び跳ねながら大きく両手を振り、いまここにいる喜びを全身からほとばしらせる。一転して、スタート直前は凛々しく結ばれた口元に、真剣勝負への気迫がうかがえた。

「登場のときに笑顔を見せるのは、自分でも初めてのことでした。レースでもそういう気持ちになれば笑顔でいきたいって前々から思っていたけれど、それどころじゃないシーンが多かったんだと思います。でもあのときは、自分はもう大丈夫な気がして。しっかりと集中できているから、ここで笑顔を見せたとしても、その感覚が途切れるわけじゃないと感じられたんです」
そこで少し言葉を切り、幸せな思い出をかみしめるように続ける。
「……場の雰囲気にのまれるときっていうのは、自分がそこにいるのを場違いだと感じたときだと思うんです。でもあの日は、自分がここにちゃんとなじんでいるって、自信がありました。心から楽しめていたし、自分自身もピークにあった。いままでの練習で自分が泣いたり怒ったりしているのを見てきた人や、支えてきてくれたみんなに『いまは大丈夫だよ、楽しんでるよ』ということを伝えたい気持ちが、とても強かったんです」
満ち足りた気持ちで駆け抜けるレースは、いままでにない感覚を田中にもたらした。
「自分でもすごく不思議に思っているんですが、なんだか、追い風が吹いていたように感じるんです。走るときはものすごく集中できていたけれど、レースと向き合っている間はずっと、夢の中にいたような気持ち。満々と張った水槽の中にたゆたい、音も光もぼんやりとしているような、世間とは隔絶されているような心地よい感覚が、ずっとありました。どうしてそんなふうに感じられたのか、いまとなってはわかりません」
レースの開催期間中、毎日細かく決められたスケジュールも、むしろ集中を誘った。一つひとつのタスクをこなしていくごとに、心が落ち着いていく。余計な物事にわずらわされず、目の前のレースと向き合うことができた。

「そんな2021年の夏以降は、イベントごとが増えましたね。いろんなレースにゲストで呼んでいただいたり、子どもたちとふれあったり……あらためて、陸上競技にまつわる喜びを味わえていると思います。そのおかげもあって、競技としてタイムを極めていくだけでなく、陸上そのものを楽しみたいと感じるようになりました。いまは、負けたり調子が悪かったりすると楽しくないって思っちゃうけど、本当に競技を愛している人はそういう浮き沈みも含めて、すべてを楽しんでいると思うんです。そういう姿勢が陸上の基本なんだなって気づいて……気づいても、なかなか実行できないんですけど(笑)」
そうやって陸上をまるごと愛せるようになれば、競技として力を尽くすだけでなく、多くの人とつながるツールにもできるはずだからと、田中は言う。
「陸上を通して人とつながれるのって、すばらしいことですよね。普段集まれないメンバーで一緒に走ったりするだけでも、すごくいい時間が過ごせる。このあいだ、同学年の選手たちとチームを組んで参加した北九州駅伝もそうでした」

大学卒業を間近に控えた2022年の冬、田中はこれまでしのぎを削ってきた仲間たちを集めて、北九州駅伝にオープン参加した。とくに高松智美ムセンビ選手とは、中学時代から何度も競い合った仲だ。大学卒業を機に競技を引退する彼女と、最後にたすきをつないだ。
「高校時代に駅伝を走るときは一区が多かったけれど、今回はじめてちゃんとアンカーをやらせてもらったんです。しかも、いいポジションでタスキが来たから……言い方は悪いけど、なんだか自分が一番楽をさせてもらったように感じています。個人的には調子が悪い時期だったので、かなり守りながらの走りになってしまったのに、淡々と進むだけで前をいけた。心身ともに強いときなら区間賞を目指しただろうけど、勢いのある高校生がまた追いついてくるのが怖くて、つい力を温存しちゃいました」
青春の1ページを語るのかと思いきや、自分の走りへの反省がのぞく。一つひとつのレースを逃さず自分の糧にしていこうという姿勢が、ひしひしと伝わってきた。

「個人競技と違って、駅伝はレースのタイミングと自分のコンディションが合わないことがあるんです。個人なら『調子が悪いんです』って正直に言えるけど、チームで出る駅伝ではそうもいきません。高校時代はとくにそうでしたが、チームのなかでエースだった場合、いっそう口にできない。自分よりもっと苦しいのに頑張っている人もいるかもしれないし、せっかく調子がいい人の士気もそいでしまう気がしちゃうんです。だから、駅伝前に調子が上がらないと、言えなくてしんどいし、言ってもしんどい。よくも悪くも、自分だけのレースじゃないんですよね。北九州駅伝では切磋琢磨してきた仲間たちと組めて、本当にうれしかったけど……自分自身に関しては、悪い部分があらわになったレースだなって思っています」


04 : ルーティン
レースでちょっとでも収穫が得られたら、
ベストが出なくても気持ちは明るくなります
彼女を支えるルーティンは多くない。なぜなら飽き性やあまのじゃくによって、いいルールを見つけてもつい手放してしまうから。でも、ひとつのやり方に固執しないそのスタイルが、むしろいい。遠征先でおいしいものを食べたり、街を歩いたり、家では飼っているインコとたわむれたり。ストレスの処理は苦手だというけれど、彼女はきちんと、自分なりの気持ちのやわらげ方を知っている。

田中は基本的に、ルールやルーティンをつくるタイプだという。でも、流れに逆らいたくなる性分は、こんなところにも現れる。
「『こうやったらうまくいく』というルールを見つけたら、まずはそれをしばらく続けます。でも、同じルールがうまくハマる場面もあれば、そうもいかないことだってある。そうすると、同じことを繰り返しているのは不吉だって気持ちになって、すごくよかったルーティンなのに『今日はあえてそれをなぞりたくない』っていうあまのじゃくな自分が出てきたりするんです(笑)。基本的には飽き性だから、同じことをし続けたくないと思ってしまうんでしょうね。とはいえ、頭は固いから不安になる。だけど行き当たりばったりでもいたい……自分でも、すごく矛盾しているなって思います。海外遠征のときなんかはとくに、ルーティンが通用しない場面も多いから、不安と期待が半々です。だったらこれまでのルールに固執しないで、その条件下でできるだけのことをやるようにしたほうがいいなって思う」

自分で見つけたルーティンを自分で手放せるのは、結局のところ、田中が強い人間だからではないだろうか。弱気になるほど、人はこれまでの勝ちパターンにすがったり、神頼みをしたりしてしまうもの。状況に合わせて柔軟になれるのは、彼女が自分自身を、芯のところで信じているからだ。
海外の遠征先では、できるだけフットワーク軽く動くようにしている。そうやって自分のなかに刺激を取り込むことで気持ちが明るくなれば、ルーティンまではいかずとも、何かしらのスイッチが得られるかもしれない。
「無理をしない範囲で、きっかけがあればなんでも乗っかってみます。練習の合間に街を散歩したり、近くで面白そうな展覧会がやっていたらのぞいてみたり。遠征先では、食べることも楽しみのひとつですね。なにを食べようかなぁって考えたり、探したりする時間も楽しい。最近は金栗記念陸上のレース前日に、チームメイトの(後藤)夢ちゃんとパフェやソフトクリームを食べました。レースは不安でしたが、そのときだけはすごく幸せでしたね」

練習や大会に忙しいなかでは、食事や散歩でさえ、貴重な気分転換のシーンなのだろう。プレッシャーのあるレースを連戦することも少なくないなかで、どのように心のコンディションをコントロールしているのか。
「やっぱり読書は、気分転換にも役立ちますね。移動中や宿泊先でも手軽に読めるから、いいリフレッシュにはなっていると感じます。でも、なかなか本に手が伸びないときもあるし、そういうときは無理に『読まなくちゃ』とかって思いたくないし……結局、本を楽しく読めるのは、そこまでのストレスがないときかもしれない」
読書で気分転換しています、と一言で済ませてしまえば楽なのに。田中は質問の一つひとつを、決しておろそかにしない。きちんと自分を振り返りながら「あの場合はどうだろう、こんな場合もあるけれど」と、丁寧に答えを紡いでいく。
「ストレスの処理は、苦手といえば苦手なほうかなと思います。これといった方法を持ち合わせていないんですよね。イライラしているときは周りに当たり散らすから、ケンカになって、わーっと叫んで……それが結果的にガス抜きになったりして(笑)。父親がコーチだから、ぶつかることも少なくありません。レースで思うように走れないときも、もちろんストレスの谷に落ちちゃいます。だけど、たいていの場合はいつのまにか、イライラが過ぎ去っている。それから、レースでちょっとでも収穫が得られたら、ベストが出なくても気持ちは明るくなります。きつい練習がこなせたときもそう。でも、場合によっては走ること自体がストレスになっちゃうんですけど……」

そんなことをまじめに話している田中の周りを、さっきから何かがピチュピチュ横切っていく。黄緑色のおちゃめなインコだ。オンライン取材の画面に何度も登場するので、かわいらしい姿に思わず「何羽もいますか?」と尋ねたら「いや、一羽が飛び回ってるんです」と、恥ずかしそうに答えた。そんなインコも、彼女をリラックスさせてくれるもののひとつだ。
「コロナ禍で家にいる時間が長くなったときに、妹が買ってきたんです。最初は赤ちゃんだったから、もっとかわいかったんですよ。いまも、家のなかに気まずい空気が流れたり、誰かがイライラしたりしているときは、鳥が間を持たせてくれます。アニマルセラピーじゃないけど、本当に癒されるんですよね」
陸上を語るときには見せない、やわらかな微笑みでインコを語る。かと思えば、頭の上に止まったインコをぱっとつかんで、躊躇なく画面の外に放り出すのも面白い。アスリートとしてではない、彼女という人間の一端が見えた気がした。


05 : 未知
これは、あのときの脚だ、
って感覚
誰も見たことのない景色に挑むためには、いままでにないトレーニングが必要だ。自分の強みを見つめ直し、未知のメニューをこなして、走りきるその感覚をみずからに刻み込む。苦しいけれど、それ以上に新しい発見があることが楽しいと、彼女は笑う。練習を積み重ねてようやく、対峙できる距離があるのだろう。
日々の練習で心掛けていることを尋ねてみると、田中は少し思考しながら「チャレンジ精神」という言葉を返してきた。一日の練習は、だいたい1時間半から2時間ほど。決めた距離を刻みながらレースペースで走り、つなぎのジョグもだらだらしないという。
「最近はいままでに踏んだことのない距離とか、スピードとか、未知のメニューに挑戦しているところです。もともと父がつくるメニューは、コンセプトは同じだけど内容は一回いっかい全部違う……みたいなメニューが多くて。でもいまは、コンセプトから本当に違うトレーニングをやっています。それが結構、わくわくするんです」

新しいトレーニングを、じんわりとうれしそうに語る。いままでは5000mをイメージした練習が多く、たとえば変化走では300mを何本も走ってトータルで5000mを目指すようなやり方が多かった。しかし、クロスカントリーや短距離もエントリーするようになったいまは、50mや150mといった変化走も取り入れている。まるでシャトルランのように、息つく間もなく短い距離を重ねていくのだ。

「いってみれば、長距離選手も短距離選手もやらないような練習をしているんじゃないかと思っています。もちろん私たちにとっても未知の内容だから、これがちゃんと効果を生むのかも正直わかりません。それに、ここまで初めてのメニューになると、やる前にきつさの予測がつかないんですよね。走りながら自分の身体の状態を見つめて、『こういう練習だと3本走ったらこんなコンディションになるんだ』とか思ったりして。毎回いろんな発見があるのは楽しいですね」
効果が出る保証のない練習を、彼女は楽しいという。感じたことのあるきつさと、感じたことのないきつさが渾然一体となる、新しい瞬間。自分が苦手としてきたタイプの負荷をうまくかけられていることだけは、確かに感じる。

「脚がガチガチになってもまだ動かすし、ほとんど休まずにすぐ走る。そういうやり方は、短距離選手に近いのかもしれません。とはいっても、短距離ではそんなに何十本も走らないと思うから……やっぱりいままでにないメニューなんですよね。でも、800mから10000mまで幅広く走るからには、しばらくそういう特殊なトレーニングを積み重ねていくのがいいんじゃないでしょうか。ある意味、自分にしかない強みを感じながら走れていると思う。細かく距離やペースを変えて練習していると『これは〇mのときの脚だ』って感覚もわかってくるんです」
レースだけでなく練習でも、さまざまな走り方をしてみることで自分の守備範囲や武器を確かめているのかもしれない。そして、練習で存分にもがいておけば、レースでは楽になる。彼女はその感覚を「レースはごまかせる」と表現した。集中しているレースでは気持ちを紛らわすことができるけれど、練習はそもそも、こなせるかわからないギリギリのラインに設定されている。だから、適当に流すことはできないし、向き合ってやりきる以外の道はないのだ。

はじめのうちは靴選びにも苦労した。信頼できる靴と出会えていないことには、自分のコンディションが安定しないのと同じくらい、ストレスを感じる。New balanceと契約をしてからも、あれこれと靴を試していた。
「私は、かかとの部分がフィットしないことが多いんです。サイズ的には合っていても、かかとのあたりがなんとなく頼りない。そういう靴だと、接地の重心がずれて走りもうまく乗れません。でも、かかとにゴルフのラバー生地を貼ってもらったり、綿と布で微調整してもらったりすると、かかとのホールド感を増すことができるんですよね。そういう調整の方法もわかってきて、かなり楽になりました。それに、最近は何もしなくても気持ちよく履ける靴がたくさん出てきたので、そもそも不自由しなくなっています。レースや練習で使い分けられるだけ、選択肢もそろって。機能とデザインが追求されきっているから、芸術品のように感じるときもありますね」

さまざまな距離を走り分けるには、さまざまな靴が必要になる。そして、いろんな靴を履きこなすための技術も、身についてきたということなのだろう。本当にフィットする靴は、相棒のように感じることもある。
「この靴さえ履けば走れるって、自信がわいてくるんです。そのときの靴は、もうただの道具じゃない。自分と一体になってくれる相棒です」
田中の近ごろの相棒は、FuelCell MD-Xだ。


06 : ギャップ
ちゃんと追いかけないと、
いつまで経ってもたどりつかない
2021年の夏を経て、彼女はまた新たなステージに臨む。自分は、何をどこまで走れるのだろうか? 陸上を味わい尽くすためには、まだまだいろんなチャレンジが必要だ。少しずつ可能性を手繰り寄せ、磨いていく行為が、面白い。彼女が2022年以降のレースとどう向き合い、いま、どこを目指しているのかを聞く。
2022年はじめての個人競技会は、全日本びわ湖クロスカントリー大会の6kmからスタート。これまではあまり練習できないまま出場したこともあったけれど、今回は、きちんとクロスカントリーを意識したメニューも取り入れた。2021年の日本選手権クロスカントリーでは、練習不足からいまいち感覚がつかめなかったという。その不完全燃焼は、ずっとどこかにひっかかっていた。
「ほかの選手は、クロカン向けの練習をしっかりできていなかったとしても、レースになったらちゃんと気持ちをつくれているような気がするんです。でも、自分の場合は、トレーニングにしっかり取り組めていないと本番にも気持ちが向かっていかなくて……。一回だけその場所を走ってみたくらいでは、練習した気にもなれないんです。だから、私にとってクロスカントリーは、いつでも走れる競技ではありません。気持ちの部分でもどうすればいいかわからないままスタートして、ぼろぼろになっちゃうこともありました。ある程度の練習ができたいまでもすごく自信があるわけじゃないけれど、今回は、練習してきただけのことは出したい。具体的な順位の目標を立てられるほど自分をよくわかってはいませんが、いま走ったらどれくらいいけるのかな、って興味はあります」

結果は、2位に52秒の差をつけて優勝。勢いに乗って日本選手権クロスカントリーに進みたいところだったが、脚の違和感で欠場した。でも、試行錯誤した練習の成果は、きっと彼女の心身になにかしらの記憶を残したはずだ。
本格的にシーズンインしてからも、チャレンジ精神あふれる走りは止まらない。1500mと5000mを研ぎ澄ましながら、今季ははじめての400mにも挑戦した。400mから10000mまで、休む間もなく大小さまざまなレースに参戦している。「10000mや800mはまだまだ初心者だし、400mは最初で最後かもしれない」と言いながら、慣れない距離に挑む楽しさのほうが勝っているようだ。

チャレンジにどん欲な姿勢が際立ったのは、4月末の兵庫リレーカーニバル。田中は1500mと10000mにエントリーしていた。1500mでは一度もトップを譲らず、4分10秒60でゴール。そのわずか25分後に、10000mのスタートラインに立った。
昨年度の日本選手権でも、800mのあとに5000mを走っている。その経験から2時間は空いているだろうと踏んでいたため、タイムテーブルを確認したときはさすがに驚いたが、辞退することなく挑戦を選んだ。
「1500mのあとに1000mという究極のスケジュールを組んだのは、その苦しさや恐怖を超えなければ、自分の殻が破れないと思ったから。練習でそんなことをする気力はまず湧かないので、大会という場を活用しました。もちろん苦しいし、怖いけれど、そもそもレースはマニュアルどおりにいかないものだから、深く考えすぎても意味がありません。しかも数十分の間に2本のレースなら、考える暇さえない。それが逆に、苦しさや恐怖をごまかしてくれました。苦しみたいのか、苦しさをごまかしたいのか結局よくわからないけど……目をつぶって突撃するイメージに近いです。そのあとで恐る恐る目を開いたら、光があるみたいな感じ(笑)」


まわりのサポートもあって、かまえていたほどには苦しさを感じずにゴールができたと、田中は振り返る。むしろこれだけのことができたから、今後どんなハードスケジュールにも耐えられる自信がついた。「逆にこれ以上のハードスケジュールはないから、次はどういうふうに自分の殻を破るか、また考えていかなきゃいけないんですが……」と、笑う。
実戦に参加することで、スタート前に同じレースに出る選手の顔を見たり、雰囲気を肌で感じたりできるのもいい。一人だけ変わった取り組みをしているぶん、よりひたむきに。このレースに賭けてきた選手たちに恥じない走りをしなければと、改めて気が引き締まる。実際にレースを経験しなければ、その種目のきつさや楽しさを語ってはいけないとも感じる。
「実戦を活用してまでいろんな取り組みをしてきたのだから、そういう自分自身にも恥じない走りをしたいんです。春先に出場した400mは出ただけで終わってしまった感もあるけれど、経験を無駄にしないために、800mや1500m、5000mのラストでは、あの感覚を思い出すようにしています。経験として、自分のなかにずっと息づくものにしたかったし、なったと思う」

そして彼女は、海外レースへも積極的に目を向けはじめた。5月にはUSATF(アメリカ陸連)ディスタンスクラシックにエントリー。アメリカ世界最高峰シリーズのダイヤモンドリーグにも、遠征を決めた。名だたるランナーがほぼエントリーしているこの大会で、みずからの現在地を問う。
「2021年夏のさまざまなレースが、本当に楽しかったんですよね。その気持ちを次に活かしていきたいと考えるようになって、視野は広がった気がします。陸上って楽しいんだ、人と関わりながら走るって、こういうことなんだ―――そのさわりの部分を味わえたというか。この世界に深く入り込んでいくために、まだまだいろんなチャレンジが必要だなと感じています」
世界での活躍を経て自分に向けられはじめた世の中の視線も、しっかりと認識している。かけられる期待とみずからのギャップが、苦しく感じることもあった。

「自分と世間の認識に、かなりのギャップがあることを感じています。さらに、自分のなかにも『ここまで走れるようになりたい』『いまはここまでしか走れない』といったギャップがあって。そういうズレは確かにしんどいですね。それに、昔よりずっと野心は大きくなっているはずなのに、素直に追いかけられなくなっているようにも思います。ただ、ここから先の目標はすべて、短期間では成し遂げられないことだから……『流れにまかせる』に戻る」と、微笑む。
つねに向かうべき先が見えていて、そのために必要なことを飄々とこなしていくような印象があった。でも、じつは彼女にもまだ、全貌は見えていないのだ。少しずつでも遠くへ行けるように、試行錯誤を繰り返しながら、前に進んでいくだけ。手探りでも慎重に、だけど大胆にやっていくために掲げた「流れにまかせる」でもあったのだろう。
「もっと、国際的に認められる選手になりたいんです。その理想をパワー全開で追いかけていくのは苦しいから、ある程度は流れにまかせて。でも、ちゃんと追いかけないといつまで経ってもたどりつかないとも思うから……ほどよく“乗れる”波があればいいなって、模索しているところです」
この文章は1999年9月4日に生まれた田中希実が、2022年5月11日まで走り続けてきた記録。そして、またここから走り出す証である。