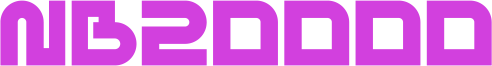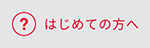New Balanceの価値観である
“オーセンティシティ(=“真実性”、“本物であること”の意)”は、
常にアスリートによって表現されます。
では、アスリートとは何か?
NB20000は、この途方もない問いに対する解答です。
【12/23(月)9:59まで】myNB会員限定 全品送料無料!
年内のお届けは12/26(木)15:00ご注文分まで! 詳細はこちら
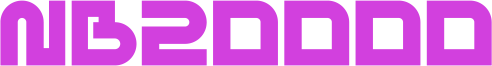 20000 words from Athlete :
20000 words from Athlete :
Nozomi Tanaka Kaede Hagitani

NB20000とは、
アスリートの本質的な魅力に触れ、保存価値のあるアーカイブを作るNew Balanceのプロジェクトです。
アスリートと向きあい、つむぎ出された言葉の数々は、文字にして20,000字超におよびます。
ときに時制を巻き戻し、瞬間瞬間の心象を紐解き、内面にせまる。
定型化した一問一答の勝利インタビューでは表現しきれない言葉を集め、群を抜いたボリュームで強さの根源を探ります。
萩谷楓
2000年10月10日生まれ。長野県佐久市立浅科中学校、長野県長野東高等学校卒業。高校卒業後にエディオンに入社し、女子陸上競技部に所属。2021年 東京オリンピック2020、2022年オレゴン世界陸上選手権 日本代表。(ともに5000mで出場)。2021年プリンセス駅伝3区1位。5000mのベストタイムは14分59秒36。
考えすぎても仕方ない。
周りを信じ、自分の直感にまかせて、進む
「ギリギリまで粘って、闘い抜く」「魅せるレースができるようになりたい」「レースが楽しみで、夜も眠れない」ーーどれも萩谷楓の言葉だ。そうやって彼女の内側をあぶりだす言葉を、彼女が走る姿だけで汲み取ることは難しい。だから、NB20000がある。
自分の気持ちを伝えることや弱さをさらけ出すことが、彼女はずっと苦手だったという。でも、信頼できる監督との出会いが、彼女を変えた。「この人となら世界を目指せる」という直感があったのだ。いまは自分の心に耳を傾けながら、素直に、楽しめそうなほうへと進んでいく。方法に迷うことはあるけれど、考えすぎても仕方ない。
彼女は何を思って走ってきたのか、そして、何を思って走っていくのか。これは2000年10月10日から、2022年8月25日までの萩谷楓に迫った記録である。

01 : 自己表現
それくらいの気持ちがあるってことを伝えないと、
走らせてもらえないと思った
萩谷楓は、自分の気持ちをうまく伝えられない子どもだったという。外ではいい子を装って、家ではそのストレスに気づいてもらおうとして、爆発することもあった。大人になってからも、自己表現は得意ではない。10代のときは気持ちを伝える手段がほかに見つからず、丸坊主にしたこともある。
萩谷楓は、大きな目をくるくると動かして、言葉を探しながら話す。関西弁のイントネーションがやわらかい。食いしばるように前を見つめて、ひたむきに脚を動かすレース中の姿とは、少し印象が違っていた。
幼いころは、バリアの強い子どもだったという。

「人をイラつかせることに生きがいを感じているような、いわゆる“ワルガキ”だったんです。でもそれは、家族や心を許している人にだけ。心を開いていない人に対しては、逆にすごく“いい子ちゃん”でした。だから、保育園に行くとすごくお利口にしていて、友達同士のケンカをやさしく止めたりするんですよね。なのに、家に帰ってきたら豹変して大騒ぎ。怒った親が外に放り出しても、反省しないで、玄関のドアを叩き続けていたそうです。根負けした親がドアを開けたら、泣きもせず、しらーっとした様子だったんですって。親が保育園の先生に相談しても『あんなにいい子なのに、そんなことないでしょう』みたいに否定されて、誰にも理解されなかったらしく……それがつらかったって、親はいまだに言いますね。『この子は将来、本当に悪い人間になるか、すごいことをやり遂げる人間になるか、どっちかや』って、よく話してたそうです」
苦笑いをして、当時のことをこう分析する。
「昔から、自分の想いを人に伝えるのが苦手なんですよね。気に入らないことがあっても、言葉で『気に入らない』とは言えない。だから、ちょっとおかしな行動をして、家族の気を引くところがあったんだと思います。外でいい子を装うぶん、家では親をイラッとさせることで、そのストレスに気づいてもらおうとする……そんな子どもでした」

走ることは、小学生時代にはもう得意だった。運動会では6年連続でリレーの選手に選ばれ、マラソン大会でも男子生徒にまざって大活躍。萩谷自身もすでにその自負があり、走ることが楽しいと感じていた。
「小学生のときは陸上クラブに入っていたけれど、別にそこまでの意気込みはありませんでした。『大会に向けて練習します!』みたいな空気があるクラブでもなかったし、のんびり鬼ごっこをしたりして、そのゆるい雰囲気が楽しかったんですよね。だけど中学には陸上部がなかったから、バスケットボール部に入部しました。バスケで基礎体力をつけて、高校からは陸上部に入る計画だったんです。バスケと並行して陸上大会に出たりしていると、けっこういい感じに走れたりして……それで、高校陸上部の先生方がなんとなく気にかけてくれるようになっていきました」
卒業後は、県内の強豪・長野東高校に進学。ところが、高校時代はしょっちゅう故障に悩まされていたという。夏のインターハイの時期までは調子よく走れるのに、秋口に差し掛かると違和感が出はじめる。寒さに弱いのか、冬にはよく脚をひきずって歩いていた。
「だからなかなか継続した練習もできなくて、思うようには結果が出せませんでした。でも、高校生のあのころは勉強がいちばん大事で、陸上はその次。もちろん好きでやってるんだけど、故障してもそこまでのプレッシャーを感じることはなかったんです。とはいえ、走ることはとにかく好きでしたね。走る以外は何もできないと思っているから、多少つらいことがあっても、辞めようと考えることはなかったです」
強い目的意識はなかったものの、肩に力の入っていない感じが逆によかったのか、萩谷と陸上の距離はじわじわ近づいていく。当時、彼女の憧れだったのは全国高校駅伝。通称「都大路」だ。高校で陸上をやると決めたときから、あの舞台で走りたかった。

「なのに、1年生のときも2年生のときもちょうど故障をしていて、出場チャンスがなかったんです。3年では『今年こそ!』と気合いを入れていたけれど、大会3週間前にケガをしてしまって……。でももう、そんなことは先生にも言えない。自分も絶対に都大路を走りたいと思っていたから、そこからの3週間はケガのことを隠したままで練習しました。だけど、直前には我慢できないほど痛くなってきて、さすがに先生に言わなきゃいけないと観念した。気持ちを伝えるために、バリカンで頭を坊主にしたんです」
家にはバリカンがなかったから、1000円カットに行った。美容師さんに坊主をオーダーしたら「やめたほうがいい」と言われたけれど、譲らなかった。冬の帰り道は、さすがにちょっと寒かった。そんな当時の経緯を淡々と振り返りながら「いまとなってはもうできないから、ちょっと尊敬しますね」と、笑う。
「大事なときにケガをしてしまったから謝罪の気持ちで頭を丸めた、とかじゃないんです。それくらいの気持ちがあるってことを伝えないと、走らせてもらえないだろうなと思ったから。自分の決意を知ってほしくて、坊主という手段をとったんですね。おかげで予定どおり、都大路を走らせてもらって、納得のいく結果も出せました」

留学生区間と呼ばれる2区を、区間6位で快走。チームの2年連続準優勝に大きく貢献した。
自分の想いを言葉でうまく伝えられないのは、小さなころからだった。でも、行動を起こすことは怖くない。他人と同じことをしても仕方がないし、自分なりのやり方を見つけたいと思ってもいる。萩谷楓の自己表現、坊主に極まれり。ちなみにこの話は語り草となっていて、いまもケガをしたりすると、監督から「坊主にするなよ」といじられる。
「都大路はいい思い出っちゃいい思い出だけど……もう坊主にはしませんよ。走ってるときはいいけど、日常生活がすごくつらかったんです。高校の女子駅伝部は全国で活躍していたから、そのうちの一人が急に坊主にしてきちゃったせいで、周りも『先生にやられたんかな?』ってなっちゃって(笑)。あのときはご迷惑をおかけしました」
毎シーズンなにかしらの故障をしてしまい、うまく練習ができなかった高校時代。周りが走り込んでいるなか、自分だけウォーキングをしているようなときには、もちろん焦ることもあった。けれど、まだ長い陸上生活ははじまったばかり。いまは土台をつくる時期だととらえて、できるトレーニングに取り組んだ。長期的な視線をもって目の前のことと向き合えるのは、萩谷の長所だろう。

高校卒業後は、実業団に進むと決めていた。いくつかのチームと話をするなかで、エディオンの沢栁厚志監督と出会う。選手として箱根駅伝やニューイヤー駅伝を経験し、現役引退後はダイハツやエディオンで陸上競技部の指導を務めてきた。
「沢栁監督とお話したとき、ビビビッときたんです。この人と一緒に世界を目指したいと思ったし、この人なら一緒に闘ってくれそうだと思いました。その直感だけで選んだから、事前にチームの合宿に参加したり、寮を見に行ったりとかは一切しませんでしたね。普通は入社一年前くらいから見学に来て、チームの雰囲気を見たりするそうです。そういうことをしなかったせいで、いまでも『萩ちゃんはなんでエディオンを選んだの?』って聞かれると、うまく答えられないんですけど。ただ、世界を目指せそうだと思ったからとしか言えない」
その直感は3年後の2021年夏、まさに実現することとなる。競技者としての勘が、このころから冴えていたというほかない。


02 : 信頼
本当の信頼は、
弱いところも見せていくことから生まれる
地道に1500mの土台をつくってきたのに、5000mで華々しい成果を出したのは、突然だった。陸上選手としての幅を広げるために、ちょっと走ってみよう。それが、萩谷楓の運命を大きく切り拓いた。専門外の5000mは自分でも不思議なくらい楽しく、思いきり走れた。壁にぶつかることもあるけれど、信頼できる監督に支えられ、彼女は今日も前を向く。
エディオン女子陸上競技部に入部した初年度は、萩谷にとって比較的おだやかな一年だったように思える。高校時代に比べて走る量はぐっと増えたけれども、故障をすることもなく、継続的な練習がようやく叶った。高校3年のインターハイで5位を獲得した1500mを強化すべく、まずはスピード練習に多く取り組んだ。
「将来的には距離を伸ばしていくつもりだったので、1500mの練習は土台作りという意識が強かったように思います。そのせいか、自分のなかでは、走る力もやることもそこまで大きく変わった印象はありませんでした。それでも一年目の夏に、いきなり結果が出た。日本陸上競技選手権大会や全日本実業団陸上で3位、国民体育大会では優勝することができました」
さらに萩谷の流れを変えたのは、そのころ専門外だった5000mでの好記録だった。2019年7月のホクレンディスタンス網走大会で、ライバルたちを引き離し、自己ベストを出したのだ。

「1500m中心でトレーニングをしてきたから、5000mを戦えるほどの力はないんじゃないかと思っていたんです。ただ、日本陸上競技選手権大会も終わったタイミングだからこれまでほど1500mに集中する必要もないし、陸上選手としての幅を広げるためにとりあえず走ってみよう、となって」
いってみれば、ちょっとした興味だったのだという。いままであまり経験のない競技で自分がどれだけ走れるのか、純粋にわくわくしながら、萩谷はスタートラインに立つ。
「これがもう本当に、楽しくてしょうがなかった。ほとんど練習もしたことがなかったから、5000mのレースは完全に未知の世界でした。どこからきつくなるのか、どこを踏ん張ればいいのか、想像すらできないまま挑んだんです。とりあえず3000mまではトップ集団についていって、あとは知らん! くらいの想定ですよ。でも、それが逆にめちゃくちゃ面白くて……先頭にくらいつけている自分がひたすら楽しいまま、走りきりました。もちろん3000m以降はきつかったし、これが5000mという距離の苦しさなんだろうなと実感した。けれど、それがそのまま『私はまだまだ距離を伸ばせる』という自信になりました」
3年も前のレースなのに、本当に楽しそうに話す。そのときの高揚がいまも萩谷の中に残り、競技と向き合うモチベーションを下支えしているのかもしれないと思えるほどだ。
長距離で予想外のいい手ごたえをつかみ、それをお守りにしながら、萩谷は中距離の練習に励む。入社2年目となる2020年には、ホクレンディスタンス深川大会で3000mの日本歴代3位に。目標としていた9分を大幅に切り、8分48秒12でゴールした。続くホクレンディスタンス網走大会では、5000mでも歴代7位のタイムをマークしている。

「練習をしていても、自分の力がじわじわ上がっているのは感じられていました。3000mで9分を切るのもずっと目標にしていたから、うれしかったですね。2021年夏の前後は、タイムを狙いすぎてあんまり力が出せないことが多かったんですが……いま思えば、このころはまだあんまり何も考えていなくて、そのおかげで記録が出せていたのかもしれないなって気がします。ただ、実業団に入ったからには、狙って記録を更新することも大事。そのバランスが難しいですね」
セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京でも、1500mで自己ベスト。上り調子のまま迎えたプリンセス駅伝では、昨年に続いて区間新を達成した。
「駅伝でタスキをかけていると、個人で挑むレースとは違う力がわいてくるのを感じます。このときは直前にケガをしていたため、そこまでスピードが出せるイメージはありませんでした。でも、とにかくチームのタスキをつなぐことだけを考えて走ったら、なぜか区間新が出た。『とにかく自分の仕事をしっかりこなす』っていう、わかりやすい目標がよかったのかもしれませんね。単純な人間だから、誰が強くて、自分はどのペースでどう走って……なんてレースプランを考えすぎると、逆にだめになっちゃう」
こともなげに振り返るけれど、彼女が一つひとつのレースで、自分自身を少しずつ解き明かしていった経緯がよくわかる。結果を出せたときのこと、出せなかったときのこと。プレッシャーを感じずにいられたのはなぜか、どうすればいいコンディションを再現できるのか?――いくつもの結果と内省を経て、萩谷は少しずつ勝ち筋を見つけていった。
そんな華々しいデビューを飾ったものの、彼女は初めての壁にぶつかってもいく。
「実業団に入って最初のうちは気持ちが強かったのか、何があっても走れるような気がしていました。何回故障しても絶対に這い上がれると思っていたし、立ち止まりたくもなかった。だけど……少しずつ、ちゃんと練習はできているのにタイムが伸びない、ということが増えてきたんです。高校時代はケガばかりで思うように練習できなかったから、ある意味でいつも言い訳があった。でも、いまはこれだけ走れているから、理由がないんですよ。初めて知る壁に、落ち込む場面も増えてきました」
ここでまた、自分の気持ちを伝えることが苦手な“ワルガキ”が、ちらりと顔を出す。
「それこそ1年目はすごく猫をかぶっていたので、実業団の先輩方からは『萩ちゃん、すごくいい子やね』と言ってもらっていました。だけど、ずっとお利口ぶってもいられなくて、2年目からは本性が出はじめた。いい練習ができなかったりすると、周りと距離をとって、自分の殻に閉じこもるんです。『私が一番つらいんです』みたいな態度をとって、察してもらおうとすることも少なくありませんでした」

親の代わりにそんな萩谷と向き合ってくれたのが、沢栁監督だった。
「監督は、私が閉じこもった殻をこじ開けてくるんです。『そんなんじゃレースは闘えんぞ』って、力ずくで。そのときはうっとうしいと思うんだけど(笑)、おかげで少しずつ、周りに頼れるようになってきました。投げ出さず、放置せずにぶつかってきてくれた監督のおかげだと思っています」
自分の気持ちをうまく表現できないから、気を許した人に甘えたり、一人でなんとか背負い込もうとしたりする。陸上競技という世界において、それでとくに困るのは、故障をしたときだ。
「周りに心配をかけたくないから、脚が痛くても誰にも言えなくて、自分だけでなんとかしようとしてしまうんです。だって、陸上選手なんだから、身体をつねにいいコンディションに保っておくことが大事じゃないですか。それが信頼につながると思っていたから、余計に誰にも故障を打ち明けられなくて……」

2021年4月織田記念の直前、周りは気づかない程度の故障をした。レース前にはとても脚が重かったけれど、それでも「調子はいいです」と言い張り、出走。結果は、もちろん散々だった。レース後にようやく正直なコンディションを伝えたとき、監督は「これからもそうやって隠さずに話してほしい」と言い、萩谷を責めなかった。
「人間なんだから、疲れているときも脚が痛くなるときもあるんですよね。いままでは嘘をついて隠していたけれど、本当の信頼は、弱いところも見せていくことから生まれるんだなって気づきました。たぶん、ダメなところを知られて見捨てられるのが怖かったんだと思う。一人で勝手に、結果が出せなかったら見捨てられるんじゃないかって思いこんでいたんです。でも、監督があるとき『萩谷が競技を辞めるまではずっと面倒見るから』と言ってくれて、もう大丈夫だって思えました」
とはいっても、いきなりすべての思いを上手に伝えられるわけではない。いまも、監督と二人、試行錯誤の途中だ。

「練習やレースが終わったあとには、かならず監督と話をします。正直にいろんな状況を伝えるべきだと頭では理解したけれど、それでもまだうまく伝えられない。ちょっとくらい脚が痛かったり疲れていたりしても、つい反射的に『大丈夫です』と答えてしまうときが多いんです。でも、監督はそれも全部わかっているから、あやしいときには『本当か?』って、探りを入れてきてくれる(笑)。おかげで助かっています」
コミュニケーションだけではなく指導も含めて、萩谷は沢栁監督に全幅の信頼を置いている。
「つねに落ち着いているし、筋の通ったことを言うんですよね。自分が正しいと思ってやってきたことを否定されるとイラッとしたりもするけれど、理屈をふまえてちゃんと話をしてくれるから、最後には納得できる。私と同じ、言葉でうまく物事を伝えられないようなタイプだったら、ぶつかりあうだけでダメになっちゃってたんじゃないかなと思います」
練習内容に納得がいかないとき、不服な気持ちも添えながら、その意味を尋ねることがある。そのほとんどは、余裕があるペース設定での練習だ。しかし、沢栁監督がその練習の意図をしっかりと説明してくれれば、萩谷も走りで、それに応える。設定タイムどおりに走れなかったとしても、練習の目的を果たしていればOK。どれだけ速く走れていても、目的を果たせていなければNGだ。丁寧なコミュニケーションを尽くしているからこそ、そうした練習が成立する。
監督と自分とは、波長が違う。だからこそ言葉を尽くさなければわかりあえない。けれどあきらめずに向き合っていれば、こうして強い信頼関係を築いていけるのだ。


03 : 武器
プレッシャーも期待も感じながら、
それでも結果を出すのが強い選手
自分の持ち味が、長いことわからずにいた。さまざまなレースを走り、世界の大舞台も経験したけれど、周りの期待には応えきれていない気がする。つい同世代のランナーと自分を比べては「あの人みたいに走れたら」と思ってしまう。でも、彼女は知らず知らずのうちに、自分だけの武器を磨きあげていた。
入社2年目の締めくくりは、日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走。女子8kmの部で、2位を30秒近くも引き離し、独走で優勝した。同レースには、そのころすでに2021年夏の5000m代表として切符をつかんでいた田中希実も出場している。
「高校時代は、長野の山でずっとクロスカントリーをしていました。だからアップダウンや足場の悪い場所を走ることには抵抗がなくて、むしろ好きなほうだと思う。だからか、このときは『最後まで先頭集団に残って勝つ』というより、『自分が前に出てレースをつくってやる』という気持ちで臨んだんですよね。普段のレースでは人の前に出ることも、誰かを引っ張って走ることもないから、まずはそういうレース展開を体感できたのがすごくよかったなと思いました。もし悪い順位になっても、あとに響くものは何もないからいっちゃおう、って思いきれたのがよかったのかな。優勝できたのもありがたいけれど、自分の走りに対してそういう新しい発見ができたことが、すごくうれしかったです。ただ、今回のレースに関しては『勝ったレース』というより『勝たせてもらったレース』みたいな気持ちが強いかもしれません」
そうはいっても、このレースは萩谷楓のレースだった。後続をぐいぐいと引き離すシーンでは、これまで内に秘めてきた勢いも感じ取れた。

「田中さんみたいに、ラスト一周で沸かせるようなレースにはやっぱり憧れますよね。そのためにはスピードだけでなく、勇気も大事。気持ちがないとあそこまでの展開はできないと思います。だからこそ、私もこれから、そういう面白いレースをしてみたい」
走ることが好きで、なんとなしに続けていたら、どんどん速く走れるようになった。強く遠い目標を持たなくても、目の前のレースと向き合うだけで、充分に面白かった。でも、少しずつ萩谷は、走ることにどん欲になっていく。
日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走のあとは、脚を痛めて走れない時期が続いた。織田記念陸上の5000mで納得のいく結果が出せず、落ち込みを引きずったまま、「READY STEADY TOKYO」に挑戦。気持ちはなかなか上向きにならなかった。
「プレッシャーも期待も感じながら、それでも結果を出すのが強い選手なんだってわかってはいるけれど、未熟なのでなかなかそうはできないんですよね。この流れじゃどうせ無理だろうから、せめていけるところまでいってみようという気持ちで走りました」
期待をもちすぎず、流れに身を委ねたときこそ速いのが、萩谷のセオリーだ。同大会では、ラスト1周前から激しいラストスパートをかけ、15分11秒84をたたき出した。大舞台の基準となる記録にはわずかに2秒届かなかったものの、彼女の存在を印象付けるには充分だったといえる。5000mと10000mで代表内定している選手たちを上回り、日本人トップをもぎとったのも、確かな自信につながった。

「もちろん15分を切れていればよかったけど、最初はそこまで迫れるとも思っていなかったんです。でも、走りはじめたときから身体が軽くて、意外と脚が動いた。1000mを通過した時点では、タイムと自分の体感が合わず、いい“ズレ”が出てきていました。ここからどうなっていくのか、このあと身体がどんな重さになっていくのかが想像できなかったから、落ち着いて進めていこうと思ったんです」
テスト大会の結果を受け、そのあとは、日本陸上競技選手権大会でどう走れるかが夏の分かれ道となる。なんとしても3位以内にくいこむべく、高地での合宿練習を重ねた。
萩谷は少し申し訳なさそうに「浮き沈みが激しくて、周りに当たり散らしていた」と、当時の重圧を振り返る。そんな精神状態に引っ張られて、いつのまにか身体が縮こまってしまったのかもしれない。日本陸上競技選手権大会の結果は4位と、ふるわなかった。
しかし、先に代表内定していた新谷仁美が、7月に入って10000mに専念すると発表。突如、5000m代表の席がひとつ空いた。READY STEADY TOYKOでの力走がワールドランキングの順位を上げてくれたこともあり、萩谷は世界と闘う切符を手にする。

「内定をいただいてから大会までの一ヶ月は、思った以上に淡々と過ぎていきました。これまでやってきた練習を変わらず積み上げて、いいコンディションをつくること。そのいい状態のまま、本番を走りきることだけが目標でした。直前の日本陸上競技選手権大会まではがっつり追い込んでいたから、そこで蓄積ができていたのもよかったと思います」
ただ、ある意味では降ってわいたような出場に、萩谷はもちろんプレッシャーを背負う。
「新谷さんの辞退があって内定したのだから、新谷さんの代わりになる走りをしなくちゃいけないと思い込んでしまったんです。すごく力がある新谷選手の代わりなんて、できない。最初のうちはそうやって視野が狭くなっていたけれど、代表に決まってから本当にたくさんの応援をいただいて……何人もの方から『萩ちゃんらしく走ってきてね』って言葉をもらったんです。それからは、一気に肩の力が抜けました。
そもそも、私がどんな経緯でレースを走れるようになったかなんて、観ている方からすればきっとどうでもいいはず。そんな経緯のためにプレッシャーを抱えるより、自分なりの走りをして少しでもいい結果を出すことが、日本代表として求められている仕事だと思いました。そのためには、いい状態で臨むことがいちばん大事。当たって砕けろという気持ちになれたおかげで、ものすごく楽しかったですね。いつか出られたらいいなとぼんやり憧れていた大会に、思いがけず2021年に出場できたことは、本当にありがたかったです。もしも2020年開催だったら、5000mのレース自体ほとんど経験していなかった私は、絶対に出られなかったと思う」

これまで積み重ねてきた努力と、多くの偶然が重なっておとずれた、萩谷の大舞台。結果は15分4秒95で、日本歴代6位の自己ベストをマークするも、予選12位で決勝進出はかなわなかった。
「自己ベストを出したのに予選落ちしたという結果に対しては、やっぱりふがいない気持ちがあります。一緒に出た田中さんは1500mで日本人選手初の決勝に進み、求められていた期待に応えたけれど、私はただ“出してもらっただけ”で終わった感じ。どうしても、気持ちがモヤモヤとすることはありました。だけど監督が『今回は、狙って出た結果じゃないじゃないか。次につながるレースになったんだから、それでいいだろう』と言ってくれたんです」
前向きな言葉かけはうれしかった。しかし萩谷は、自分のなかにふつふつと湧き上がる、陸上への情熱にも気づきはじめる。
「田中さんみたいにラスト何秒で会場を沸かせるレースもしたいし、廣中さんみたいに先頭で引っ張るようなレースもしたいんです。でも監督にそう言ったら、萩谷は萩谷の魅力を新しくつくっていけばいい、と言われました。レースを引っ張ったり盛り上げたりするのも大切な役割だけど、陸上選手の魅力はそれだけじゃないんですよね。とはいえ、自分らしい魅力なんて思いもつかなかったけれど『ギリギリまで粘って、どこまでいけるんやろうって思わせるのが萩谷の魅力や』と言われて……二番手にぴったりついて、ずるくてせこい走りかもしれないけど、それでもギリギリまで闘う。それって私の武器やったんや、私にもちゃんと武器があったんやって、初めて気づきました」

萩谷は、自分がすごく欲張りになってきたみたいだ、と続ける。
「私の持ち味はちゃんと大切にしながら、その先ではやっぱり、魅せるレースもできるようになりたいんです。世界で闘っていくにはそれも必要だから。いまはとにかく気持ちを楽にして、できることをひとつずつ積み上げていくところからはじめようと思っています」
出場経験を経て、世界の場で力を出せることが、何よりも一番強いと感じるようにもなった。「ほかの大会で速かろうが遅かろうが、世界中の選手が集まる4年に一度の大会で、きちんと結果を出すこと。そこに向かってコンディションを整えていくことが、何より難しくて大事なんじゃないかなと思っています」と、遠くを見据える。


04 : 孤独
走っているときはつねに孤独だけど、
その孤独はランナーに必要なものだと思う
いい練習ができているときは、早くレースを走りたくてうずうずする。遠足に行く前の子どもみたいに、楽しみで眠れない。だけど、走り出したらたった一人。ランナーは孤独だ。それでも気持ちを奮い立たせて進めるのは、周りの支えがあるから。スタッフも、家族も、彼女の心に寄り添っている。
特別な大舞台を越えても、日々のトレーニングがことさら変わることはない。広がった視野や新しく生まれた情熱をもって、こつこつと取り組むだけだ。
「普段の練習では“プラスα”を大切にしています。60分のジョックなら65分走る、72秒の練習なら70秒を切る、みたいな。いつでも100%の力を出すために、ほんの少しでも先を刻んでいないと怖いんですよ。練習を95%でやっていたら、本番でもそっちに引っ張られてしまう気がする。エディオン女子陸上競技部では、そこまで難しいトレーニングはありません。普通に取り組んでいれば、ちゃんと100%でこなせるメニューを組み立ててくれています。だからこそ、自分のなかにプラスαが必要なんです」
監督からプラスαを押しつけてくることはない。でも、萩谷がやりすぎているのを、逆に制されることはある。先日はレースの数日前にも関わらず、調子がいいからと90分もジョックをして、叱られた。でも、それくらい気持ちよく走れるときはレースの結果もよかったりするんですよと、いたずらっぽく笑う。

「ただ、練習はそんなに好きじゃないですね。適度にサボったりもしているから、周りからはサボり魔だと思われている気がしてたけれど、こないだ『つねに高いレベルで練習をこなしてる』って言われて、びっくりしました(笑)。ただ、練習はともかく、レースは出れるものならどんなレースも出たいと思っています。レースってとにかくきついし、最中は何が楽しくて走ってるんやろと思ったりもするけど……やっぱり、いい結果が出たときの達成感は何物にも代えられなくて。それを味わいたいから、走ることを辞められないんだろうなって思います」
ただし、好きでも緊張はする。数日前からドキドキするから、当日を迎えるころには自然と身体が緊張に慣れ、意外と落ち着いているらしい。
「とくに、いい練習ができているときは早く走りたくてしょうがないんです。前日の夜はもう、楽しみで眠れない。遠足に行く前の子どもみたいですよね。逆に、不安なときはよく眠れます。睡眠具合で、いまレースに臨んでいる自分の状態を見ているところもあるかもしれません」
いまはワクワクをにじませて話しているけれど、実際に走り出してしまったら、ランナーは孤独だ。たった一人、己のリズムに耳を澄ませて、脚を動かし続けるしかない。
「練習をしているときも一人でいることが多いのは、あえて自分からそういう孤独をつくっているからかもしれないですね。駅伝は団体競技だけど、走るのは自分一人。個人レースならなおさらです。球技なら交代できることもあるだろうけど、陸上競技はスタートしたら、誰も助けてくれません。どんな状態だって前に進まなきゃいけないし、タスキを渡さなきゃいけない。走っているときはつねに孤独だけど……その孤独は、ランナーには必要なものなんじゃないかなって思っています」

たった一人で走っていて、不安になることはないのだろうか。レースでも練習でも、周りが見えずに焦ってしまうことは? 自分はこのままでいいと信じるためには、どうすればいいのだろう。
「世界で闘えるレベルにいくためには孤独が必要だと思っているし、みずからその状態を選んでいるんだけど……気持ちが不安定になったとき、助けてくれるのはやっぱり周りのスタッフなんです。いつだって気にかけてくれるし、必要以上に内にこもりすぎていれば、無理やりにでも引っ張り出してくれる。そんな周りを信じているから、私も安心して孤独でいられるのかもしれませんね」
もうひとつ、萩谷の孤独を支えるものは、同じく孤独と向き合うライバルたちの存在だ。同世代の選手の活躍を見ると、若者らしく心がざわざわする反面、ポジティブな闘志も湧き上がる。
「同じレースに出るとなったら、絶対に負けたくないと思います。でも、自分が走らないレースでいい結果を出しているのも、目に入るとくやしい。遠いフィールドで活躍されちゃったら、私はどうすることもできないじゃないですか。こういうライバル意識は認めたくない自分がいるから、普段は言わないけど……やっぱり気にはなっちゃいますね。私は気持ちが入りすぎるといいことないタイプだし、なるべく考えないようにはしているんですが」
近ごろはもう、誰がどのレースをどれくらいで走ったかはあえて見ないようにしている、と笑みをこぼす。

そのほか、萩谷をかたちづくり、陸上をはじめたころから今日まで寄り添ってきた家族の存在も欠かせない。母親の朱見さんは、かつて自身も実業団で走ったランナーだ。自分の苦しみを理解してくれる家族が、いつも黙ってその闘いを見守ってくれていることは、どれほど心強かっただろうか。
「しょっちゅう連絡は取りあっているけれど、競技に対してあれこれ言われることはないんですよね。レース後なんかはとくに、良くても悪くてもとくにコメントはしてこない。それは、私にとってはすごく心が楽です。『今回はこうやって走ったほうがよかったんちゃう?』とか『あそこでなんで前に出なかったん?』とか、きっと思うことはいっぱいあるだろうけど……母もランナーだったから、気持ちを分かってくれているんだと思います。そのぶん、納得のいくレースができなかったときは、母のことも満足させてあげられなかったような気がして、申し訳なく感じちゃうんですけどね」
決めたことは最後までやり遂げる――昔から親に教わってきたことは、それくらいだ。何かを強制されることはなく、いつでも萩谷の決めた道を応援してくれた。「いま陸上を辞めたいって言ったら、いろいろ言うてくるかもしれませんけど」と話しながら萩谷もどこか誇らしそうで、親への信頼感がのぞく。
2020年のクイーンズ女子駅伝の前には、2歳違いの姉がピアスをプレゼントしてくれた。「レースの先行きを見通せるように」と願いを込めた、れんこんのピアスだ。
「願を掛けるとその内容を意識できるし、なんとなくよさそうじゃないですか。でも、そのクイーンズ駅伝はあんまり結果がよくなかったから、れんこんには恨みしかないです(笑)」
そう笑いながらも、ピアスに願掛けする習慣はまだ続いている。粘り強く走れるようにと、日本陸上競技選手権大会では刻んだオクラ。日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走では「新しい自分にジャンプアップするために」と選んだ、金色のかえる。頭角をあらわせるようにかたつむり、つねに上に登っていく習性があるというテントウムシ……。
「恥ずかしがりやだけど目立ちたがりでもあるから、萩谷といえばこれっていう印象をつけたくて、続けてます。でも、いいピアスを探すのが大変だし、最近はネタ切れですね」
幼いころから地道に走ることを続け、輝かしい成績を次々に残しているけれど、まだ20歳を少し過ぎたばかりなのだ。トレードマークのボーイッシュなショートヘアに水を向けてみると、これまで以上にくだけた表情で話しはじめる。

「髪の毛を伸ばしてみたいってずっと思ってるんですけど、なかなかうまくいかないんです。高校時代は部員が全員ショートだったから、実業団に入ったら伸ばすって決めてたのに、ついうっとうしくなって切っちゃう。去年は成人式があったので、自分なりにはがんばって伸ばしたんだけど、それでもあごのラインをこえられませんでした。いままた我慢して伸ばしてるところなんだけど、みんな『楓ちゃんはショートが似合う』とか言ってくるから、決意がゆらぐ……」
2021年から契約しているNew Balanceは、アスリートやスポーツより、タウンユースのイメージが強かったという。自分もそのブランドをまとえることが、単純にうれしかった。
「私よりも先に契約していた田中さんが、いつもかわいいユニフォームを着て走っていたから、お話をいただいたときはすごくうれしかったですね。街を歩いていても、New Balanceのスニーカーってすごくよく見かけるし、おしゃれだから。私自身はこれまではあんまりファッションに興味がなくて、合宿の移動なんかでもいつもジャージを着ているような生活をしていたんです。でも、エディオン女子陸上競技部に入ってからは、電車や飛行機に乗るときはある程度ちゃんとした格好をしないといけないと思って。スキニーにTシャツにスニーカーみたいなシンプルな格好が多いけど、いわゆる私服というものをようやく買うようになりました。でも、プライベートの洋服も、買ってみたら買ってみたで楽しい。すっごいおしゃれがしたいわけじゃないけれど、自分の似合う服や心地よい服を見つけて、ほどよくファッションも楽しんでいきたいなって思ってます。New Balanceのパーカーやパンツは、動きやすいのにかわいくて、気持ちが上がりますね」


05 : 距離
5000mは中途半端な気持ちでは走れない種目だな、
という印象です
さまざまな距離を走るからこそ見えてくるものがある。それぞれの距離に、思い入れがある。面白みもある。自分をひとつ上のステージに引き上げてくれた5000mもそうだ。結果を出せたレースが多いぶん、プレッシャーもあるし、中途半端な気持ちでは走れない。
実業団に入り、本格的にランナーとしての道を歩みはじめて4年。いくつもの好記録を出し、世界的な大会への出場を果たすなど、滑り出しは好調だ。それは、昔からなじみのある1500mや駅伝だけに固執せず、5000mなどにも果敢に挑戦し、みずからの幅を広げてきたからともいえるだろう。萩谷は、それぞれの距離にそれぞれの面白さがあると語る。
「1500mは高校時代から一番多く走ってきた種目なので、そのぶん、自分の成長も目に見えるところが面白いです。最近は年に一度くらいしか機会がなくなったから、余計に楽しみながら走れるようになりました。入社1年目で1500mばっかり走っていたときはあんまりスピードが出せなかったのに、最近は徐々にタイムも縮められていて……去年も全日本実業団で走ったけれど、練習していないのになぜかベストが出せた。ただ、800mなどを多く走っている選手にはスタートダッシュで勝てないし、難しい競技だなとは感じています。練習も大変で、300mみたいな絶妙な距離でインターバルをやったりするんですよ。200mだったら短いから頑張りがきくし、400mで少し落ち着いたペースで走るならいいけど、300mはきつい……」
実業団に入りたてのころの、厳しい練習を思い出しているらしい。でも、その積み重ねがあったからこそのいまだと感じていることは、表情からも見て取れる。

「3000mで世界一を競う機会は少ないけれど、だからこそ逆に、極めていきたい気持ちがありますね。こういう部分を地道に頑張っていくことで、1500mや5000mのベースアップにもつながっていくんじゃないかなと思っています。レースで大きく失敗した記憶もないし、トラック7周半で終わると思えば、苦しいといってもギリギリ気持ちが保てる。だから、比較的ポジティブな気持ちで取り組める距離だと感じています」
次に、実業団ランナーとなってから飛躍的な成長を見せた5000m。この距離と出会っていなければ、いまの萩谷の活躍はないだろう。
「5000mはきっと、今後いちばん走っていくんでしょうね。世界の舞台で走らせてもらったことも、陸上選手として本当にかけがえのない経験になったと思っています。でも、5000m、きついんですよね……(笑)。やっぱり1500mや3000mにはない『距離のきつさ』があります。3000mを過ぎてからの走りは、とくにいまの自分の課題です。世界を見据えていくと、15分ちょっと切るだけじゃ通用しないから、どんどんレベルを上げていかなきゃいけないっていうプレッシャーもあって。いまのところ結果を出せたレースも多いし、走りたくないわけでは全然ないんだけれど、スイッチを入れるのに少し時間がかかるというか……中途半端な気持ちでは走れない種目だなという印象です。走っていて苦しいときは、監督の顔がよく思い浮かぶんですよ。いつも鼓舞してくれる監督のために、という気持ちが支えになる瞬間はけっこう多いですね」

たった一人ですべてを背負う中長距離に対して、クロスカントリーや駅伝では、シンプルな楽しさが勝つようだ。
「走っていて、いちばん純粋に楽しいのはクロスカントリーですね。アップダウンが好きなのもあるし、不整地の感覚も面白い。高校3年間の積み重ねがあるから、変化の多いコースのほうがリズムに乗れるんだと思います。駅伝も、やっぱりチームのみんながいるのは特別。想いをタスキでつないで走るのは、楽しいだけでなく心強いです。5000mのつらいときは自分や監督のためだと思って走るけど、駅伝はチームのみんなのことを思い浮かべられるのが、うれしくもあります」

さまざまな距離を走りながらも、シューズはいつもLD-Xを使う。曰く「もともと靴に対してそこまで繊細ではないから、気に入ったものを履き続けるタイプ」。実際、クロスカントリーでスパイクを使ったり、1500mをマラソンシューズで走ったりしたこともあるという。
「最近だと、前バージョンから履かせてもらっているFRESH FOAMが気に入っています。ホールド性が上がったし、アッパーのやわらかさもしっくりくる。前は少しやわらかすぎて足が遊ぶ感じがしたけれど、ぐっと良くなりました。ちょっと幅広になったからか、安定性もより増した気がしています。そうやってシューズに対して信頼をもてるようになったのは、自分のなかでもここ数年の大きな変化ですね。トレーニングに合わせていろんなシューズが試せる、履けるレンジが広がってきているのも、競技にとってプラスになると感じています」


06 : 気持ち
軽々しく走りたいなんて言えないのもわかっているけど、
どうしようもなく惹かれてしまっている
「走りが気持ちに左右される」と、何度もこぼす。昔はその状況をうまくコントロールできなかった時期もあったけれど、いまは、それも含めて自分だと受け止めている。落ち込んでいたっていつかは元に戻るのだから、あんまり考えすぎず、淡々とやっていけばいい。きっともっと先までいけると、彼女は自分を信じている。
コロナ禍に入ってからは、思うように活動できない場面が増えた。もともと一人で練習するのを好んでいたとはいえ、少なからずストレスはあっただろう。それでも、2021年の夏前後ではきちんと結果を出せている。一人きり手探りのようにする練習でも、ちゃんと目的をもって動けていれば大丈夫なのだと、自信になった。
「あらためて振り返ってみると、私は本当に、走りが気持ちに左右されるんだなと感じます。そこそこ長く走ってきたのに、それに気づけたのは去年のことなんですよ。いままでは、ちゃんと練習できていないときか、いけいけどんどんのとき、その2種類しかなかったから気づかなかったのかもしれません」
たとえば、狙いすまして臨んだ代表選考レースではだめだったのに、直後の全日本実業団では、5000mでさらりと15分を切っている。ここまで話を聞いてきたかぎり、その結果はじつに萩谷らしい。それまでほとんどできていなかった走り込みを練習に加えたことも理由のひとつだが、いままでと大きく違うのは、萩谷自身が気持ちの与える影響の強さに、はっきり気づいていることだ。

「調子が悪いとき、ずーんと落ち込んでしまう自分にはもう慣れました。季節の変わり目に脚が重くなったり、ふがいない状況に引っ張られて一日じゅう悩んだりしちゃうのも、もうしょうがない。でも、そういう不調は全部、時間が経てばちゃんと元に戻ることもわかったから。あんまり考えすぎず、淡々とやっていければいいと思っています。たぶん、走ることさえ嫌いにならなかったら、大丈夫なんじゃないかな。『ここで記録を出さなきゃ』って思い詰めすぎると、普段の練習から『これをやらなきゃ』『あれもやらなきゃ』になってしまう。でも、単純に走ることが好きで、楽しいと思えていれば、そういうしがらみを忘れて肩の力が抜けるかなって気がします」
そのためには、いい練習を積み重ねることがすべてだという。いい練習ができて、少しでも上向きの調子に乗れていたら、その波に乗ってレースも快走できる。落ち込むとひきずるタイプではあるけれど、前日までの気持ちよく走れた感覚をそのまま持っていけるのは、メリットでもあるのだ。
「プライベートでは、ゾンビものや戦争映画を観たり、温泉をめぐったりするのが好き。地元の長野に暮らしているときはそこらじゅうに温泉があったから、ジョックで温泉に行って、帰るときに親に着替えを持ってきてもらったりしていました。いまもサウナは好きですね。汗をかきすぎるとよくないから、あんまり頻繁にととのうわけにいかないのが残念です。でも、温泉やサウナに入っていても、つい陸上のことばっかり考えちゃう。誰がどう走ったとか、私はどうするべきかとか、考えたくないのに頭のなかがいっぱいになっちゃうこともあって……もう、いまは仕方ないかなってあきらめてます」

2022年度は、5000mの織田記念陸上からスタート。その1週間後の日本陸上競技選手権大会にも、はじめて10000mでエントリーしている。好記録を出せば、夏のオレゴン世界選手権も射程距離に入ってくるというレースだ。
「あとに続くさまざまなレースにつなげていくために、まずは10000mを体感しておきたい。今年すぐに10000mで結果を出せるとも思っていないです。……とかいって、そういうラフな気持ちで臨んだほうがいい走りができそうだし、途中でもっと気持ちがアグレッシブになる可能性もありますが」
やんちゃな微笑みだ。いまみたいな心持ちが、萩谷にとってはいちばん走り心地がいいのだろう。2021年の夏以降、大きな故障もなく日々の積み上げができているのも、よりどころになっている。このまま少しずつスピードを上げて、勢いに乗り、シーズンを迎えたい。
高校時代からずっと「少しずつ伸ばしたい」と考えていた距離も、ついに10000mまで届きつつある。ここからさらに、萩谷はどこへ走っていくのだろうか。

「陸上をはじめたときから、最終的にはマラソンをやりたいと思っていました。実業団ランナーだった母もそうで、マラソンまでたどりつきはしなかったんだけど、その想いは昔から聞いていて。別に代わりに走るような意識はないけれど、純粋に、親も見たことのない景色を見てみたいなって思っています。じつは監督とも、冗談まじりに『パリではマラソンか?』なんて話をしていて……今年もいくつかマラソンの大会を見せてもらったんですが、なんだかもう、フラットな気持ちでは見られなくなっちゃったんです。レース展開を素直に楽しんだり、応援したりできなくて、自分が走ったらどうなるかみたいなことを考えてしまう。いままでマラソン練習なんてやってこなかったから、軽々しく走りたいなんて言えないのも分かっているけど、どうしようもなく惹かれてしまっている自分がいます」
未知の5000mに挑んだときのように。これまで経験のない大舞台で、自分なりの走りを見せようとしたときのように。萩谷の大きな目が、期待と少しの不安をにじませてくるりと動く。
「来年から少しずつ、マラソンもはじめられたらと思っています。いままでは35kmまでしか走ったことがないから、レースに耐えられる身体ができているかは不安です。あと10kmくらいならなんとかなるんちゃうかと思いつつ、そんな甘いものではないことも感じています。監督は、まだ待てって言いますね。私も今後長く競技を続けていきたいと思っているし、そんなに焦ってはじめなくていいのはわかるんですけど……それでもやっぱり、やりたい」

すでに花を咲かせつつある5000mに集中して、タイムに磨きをかけるべきだという声もあるだろう。でも、これだけうれしそうにマラソンを夢見る萩谷を目の当たりにしても、外野は同じことが言えるだろうか?
「勘なんですけど、マラソンは自分に合っているって思うんです。ある程度の時間をかけて、きついところで粘りながら押していくのが私のやり方だから、マラソン向きかもしれないって。本当にただの感覚なんですけどね」
ただ、彼女の直感は馬鹿にできない。そして、入社2年目のクロスカントリー選手権。並みいる強豪選手をねじ伏せて、気持ちよく風を切る萩谷の姿を思い出した。彼女が彼女らしい走りを見せていくフィールドがさらに広がるというのなら、そこには期待しかない。
「2021年の夏以降、私を取り巻く環境は大きく変わりました。地元の長野や競技場に行くと、ちびっ子たちが私のところに『サインください』って来てくれるんです。すごくうれしい反面、私でいいのか申し訳ない気持ちがありました。いつも恐縮していたら、母に『いまはそう思うかもしれないけど、これからもっと強くなって、サインを受け取った子どもたちが自慢できるような選手になっていけばいいやん』って言われたんです。じつは私も小学校低学年のとき、上野裕一郎さんにサインをいただいたことがあったんだけど、当時は上野さんがどのくらいすごい選手なのかわかっていなかったんですよね。それでも、少しずつ上野さんのすごさを知るにつれ、サインを持っている自分が誇らしくなって。いま私の前に並んでいる子どもたちも、私が何をした人なのか、どのくらいのタイムで走っているかなんてきっと知らないだろうけど……いつか私のサインが、自分にとっての上野さんのサインみたいなものになっていったらいいなって思えました。いまは予選落ちの萩谷だけど、これからメダルを獲ったり、優勝したり、その子たちが誇らしく思えるような記録を積み重ねていきたい。『誰やこのサイン』って言われちゃう日がこないように、がんばります」

すでに鮮やかな足跡をいくつも残していて、これからの伸びしろも充分に持っているのに、萩谷は謙虚だ。色紙どころか、帽子や靴を持って並び、油性ペンでサインを入れてくれと頼んでくる子も少なくない。そんなとき、萩谷はドキドキしながら、ペンをとる。「これ、レースのときに履くやつやろ? って、ちょっとプレッシャーを感じながら、小さく書いちゃいます」と、困ったように笑う。
彼女がどこまで走っていけるのかは、まだ誰にもわからない。
この文章は2000年10月10日に生まれた萩谷楓が、2022年8月25日まで走り続けてきた記録。そして、またここから走り出す証である。